
2025年春、突如訪れたコメ価格の高騰。
スーパーだけでなく、薬局やコンビニからも全てのコメが無くなり、やっと並んだかと思えば、5,000円/5kgという破格の値段。
物価高が進む現代の日本、何とか自炊でやりくりしようと頑張る若者にとって、非常に痛手。米の消費を抑えるべく、焼きそばや豆腐系をメインにした料理で凌ぐ人も多い。
そこから、備蓄米放出などを経て、米価格もようやく落ち着きを見せてきた。
対して最近、その米の栽培環境を破壊する「オオバナミズキンバイ」という生物が話題に。また米不足が再来されては困る。そう思い、この謎の生物について調べてみた。
(参考) “コメ”を脅かす最強級外来種「オオバナミズキンバイ」除草剤が効かない!? 小さな破片からも再生する脅威の繁殖力https://news.yahoo.co.jp/articles/7bb271b7473c3fa542220a022a39c34ed4d7b091?page=1
オオバナミズキンバイとは?

特定外来生物ーオオバナミズキンバイーの位置づけ
オオバナミズキンバイは、2014年に特定外来生物に指定された植物で、南アメリカを原産地としている。外来植物の中でも特に侵略的とされる種類で、日本の生態系や農業に深刻な影響を与えているよう。
特定外来生物に指定されたことで、輸入や栽培などが法律によって厳しく規制されているが、すでに国内での拡散が進んでいる地域も多くみられる。
見た目の特徴と分布範囲
オオバナミズキンバイは鮮やかな黄色い花を特徴とする水生植物。
見た目は美しいものの、その繁殖力は驚異的。適応能力も非常に高いため、水田や川、水路といった水場を中心に急速に広がっている。陸上でも成長が可能で、多様な環境に適応する力を持つ。日本では、特に三重県桑名市をはじめとした地域でその存在が確認されており、田んぼや農業用水路に多大な影響を及ぼしている状況。
綺麗なモノほど毒がある。

侵略的外来種としての問題点
オオバナミズキンバイは、単なる「美しい植物」として見られるべき存在ではない。その繁殖によって在来種を駆逐し、植物や野生動物の生態系を攪乱するほか、農業においても深刻な被害をもたらしている。
具体的には、田んぼ半分を覆い尽くすほどの成長スピードで、コメなどの作物の栽培に必要な環境を破壊。また、水路の通水に障害を生じさせることから、地域の水管理機能にも影響を及ぼす。
過去の日本での侵入および拡散状況
オオバナミズキンバイが日本で最初に確認された時期については不明な点も多いが、三重県桑名市では約3年前に初めてその存在が見つかったとされている。その後、成長と繁殖が急速に進み、現在では田んぼや水路に大きく広がっているよう。
除草剤などを用いて駆除が試みられたケースもあるが、茎や葉が切断されても再生する強い生命力により、完全な除去は困難を極めている。
脅威となる繁殖力のオオバナミズキンバイのメカニズム

分裂や再生能力による驚異的な生存性
オオバナミズキンバイは、非常に高い繁殖力を持つ外来植物。この植物は茎や葉が切断されても、切断面から再生する能力がある。つまり、駆除のために物理的に取り除いたとしても、その破片から再び増殖する可能性があるということ。
このような驚異的な再生能力により、オオバナミズキンバイの完全な駆除は非常に難しくしている。これが、田んぼや水路といった農業用地に広がる要因の一つとなり、私たちの生態系や環境に甚大な影響を与えている。
生態系への影響は?
オオバナミズキンバイは、繁殖力の高さから急速に分布を広げるため、在来植物を圧倒し、自然の生態系を大きく変える。この植物が大量に生い茂ることで、光や栄養分、水分を奪われた在来植物が生育できなくなることがある。
また、環境に生息する野生動物にも影響を及ぼす。特に水生生物は、オオバナミズキンバイが密生することで生息環境が変化し、棲み処を失う恐れがあるよう。こうした影響が積み重なることで、生態系全体のバランスが崩れ、地域の自然環境が脅かされるとのこと。
実際に見られているオオバナミズキンバイの影響と被害例

事例1:環境保全地域での生態系攪乱
オオバナミズキンバイの侵入は農業分野にとどまらず、生態系にも多大な影響を及ぼす。環境保全地域では、在来植物がこの外来植物に圧倒され、数を減らしている状況が確認されている。
また、水生植物に依存する在来の野生生物にも影響を与えており、生態系のバランスが乱されている。あっという間に広がることから、元々その地域に生息していた水生生物や植物が生存の危機に直面する事態となる。
事例2:地域住民に与える影響
オオバナミズキンバイの繁殖は、地域住民にもさまざまな影響を及ぼしているよう。例えば、農家ではコメを含む農産物の生産量の減少につながっているほか、水田や用水路の管理作業が大幅に増えるといった問題も発生している。
また美しい花を咲かせる見た目とは裏腹に、住民が管理しきれないほど広がることで、地域全体の環境資源を損なう恐れも指摘されている。さらに観光名所として魅力的だった湿地帯や自然公園でも生態系が破壊されるケースがあり、観光業にも間接的な影響が出ているとのこと。
対策と私たちにできること

『入れない、捨てない、拡げない』の原則
オオバナミズキンバイの対策として重要なのが、「入れない、捨てない、拡げない」という原則の徹底。
これは、外来種が新たな環境に侵入したり、既に侵入している場所からさらに拡大することを防ぐための基本的な方針。
具体的には、オオバナミズキンバイの種子や茎を誤って移動させることがないよう、釣り具や農機具などの清掃の徹底が必要。
環境省や地方自治体の取り組み
環境省や地方自治体も、オオバナミズキンバイの駆除に積極的に取り組む。特定外来生物として指定されたオオバナミズキンバイは、法的な規制の対象であり、輸入や飼育、販売などが禁止されている。
さらに、地方自治体では行政主導の駆除活動が計画され、駆除作業の参加者に向けた説明会や活動結果の共有が行われている。これらの取り組みは、地域社会と行政が連携して問題解決に向かう好例となる。
長期的な予防策
オオバナミズキンバイの駆除や拡大防止のためには、長期的な予防策と教育活動が不可欠。この外来種に関する情報を積極的に共有し、地域住民や農業従事者にその影響について理解してもらう必要がある。
特に、学校や地域イベントを通じて生物多様性の保全の重要性を学ぶ機会を設けることで、次世代の子どもたちが環境問題に意識を持つきっかけを提供できる。
特に小さな子供は、興味本位でオオバナミズキンバイに近づいたり触ったりしそう。小学校での教育は必須。
まとめ

オオバナミズキンバイを含む外来種の問題は、一地域だけではなく社会全体の課題として認識し、対応していくことが不可欠。そのためには、「入れない、捨てない、拡げない」という基本原則の徹底だけでなく、地域住民、農業関係者、行政機関、NPO法人などが協力して取り組む防除活動が求められる。
たとえば、駆除作業に市民が広く参加できる仕組みを作り、補助金制度などを活用することで、活動の継続性が高まる。
また、定期的に活動報告を行いながら、進行状況や成果をコミュニティ全体で共有することで、意識を高め合うことも重要。未来型の防除活動では、こうした地域社会全体の協力体制が鍵となる。
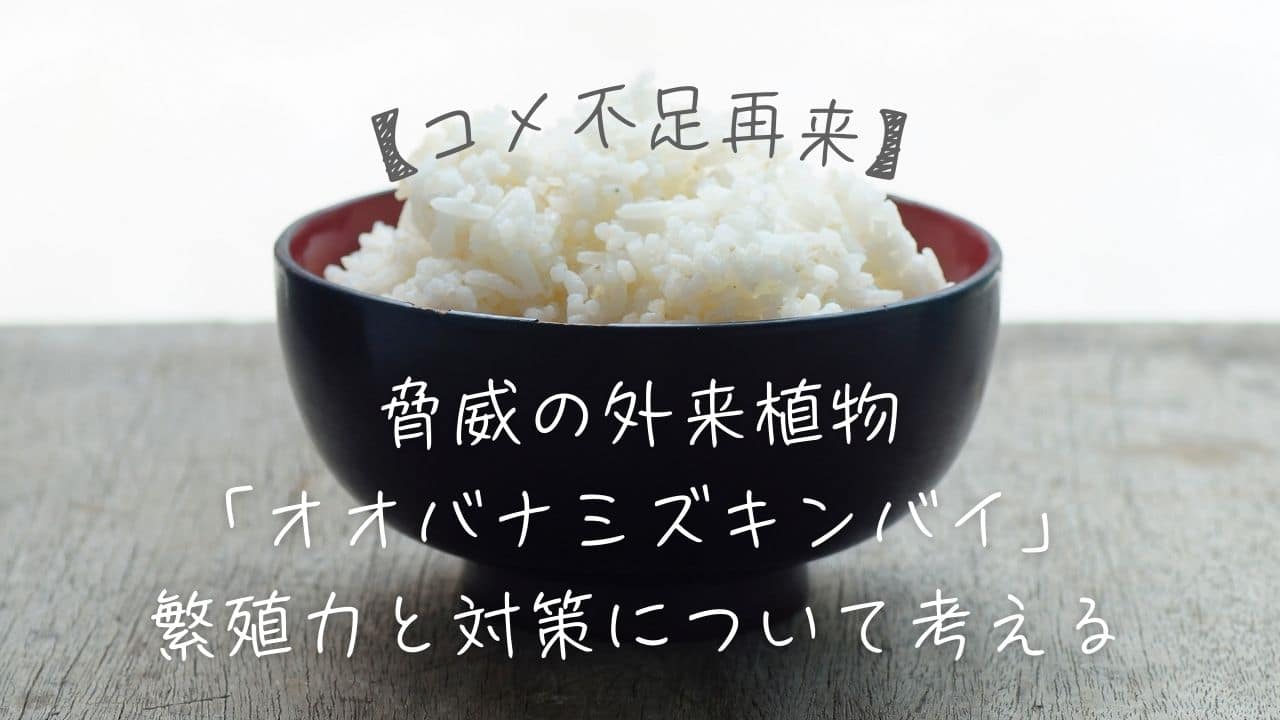








コメント