今やインタネット上でエントリーシートを出すご時世。膨大な量のESを確認することが難しい企業側にとっては、”学歴”だけで人物を判断することも珍しくないです。
就活生の中には、大学生の時に色んなことを頑張ったにも関わらず、最終学歴がネックとなり、選考に進めない人もいるでしょう。
そこで私は、最終学歴を変えるために猛勉強に励み、偏差値50以下の私立理系→国立の大学院へ学歴ロンダリングしました。
本記事では、学歴ロンダリングまでの流れと実際に就活では有利となるのかを、経験を元に解説。
長くなるので、大学院入学まで(前編)と入学後から就職まで(後編)に分けています。記事の最後に(後編)のリンクを貼っているので、そちらも見て欲しいです。
学歴ロンダリングした私の経歴
初めにロンダリングした私の経歴を紹介します。
- 物理学専攻/TOEICのスコアは655
- 偏差値50以下の私立理系→ 大阪大学大学院へ学歴ロンダリング
- 内部進学生に負けじと2年間本気で研究生活に没頭
- 修士卒で従業員2万人以上の巨大企業に就職
学歴ロンダリングの難易度

結論、大学入試と比較して圧倒的に進学しやすいです。理由としては、以下の通りです。
受験教科が少ない
通常、国公立の大学院へ進学する場合には5教科7科目が必要。私立でも、平均3科目の試験があります。対して、院試にはそのような大量の試験を受ける必要がありません。
一般的には専攻分野1〜2科目や、専門分野1本のみが多いです。
物理学専攻の私は、解析力学/電磁気学/量子力学の大問が1つずつといった形式で受験。志望大学院の受験科目を事前に把握・対策することで、点数は確保するのは不可能ではなかったです。
また、英文読解が加わるところも多いです。私も英語の大問を1問解きました。その大半が専門分野に関する英文のため、専門分野に関する英単語さえ抑えておけば、何とか読めるレベルには到達できるでしょう。
また、TOEICのスコアが必要な研究室もあります。私もスコアの提出したが、何点以上必要といった制限はありませんでした。ただし、スコア730以上が求められる研究室もあり、専攻によって差があるも事実です。
後に説明する研究室訪問の際に、詳細を確認しておきましょう。
面接のみの研究室も
筆記試験がなく、面接のみの研究室もあります。この場合、学部在学時の成績(GPA)やその専門分野に対する知識が問われます。
大学院進学後に何をしたいかや、これまでの興味からなぜこの研究室を選んでいるのか等、就活に似た質問が飛んできます。この時、最終学歴を変えたいからという気持ちで臨むと、面接官に速攻見抜かれて、図星を突かれるので注意です。
(参考)実際に聞かれた質問とその回答
Q1.「なぜ量子力学を勉強しているのですか」
A1.「私たちの目に見えている光景が全て量子力学によって成り立っているから。例えば、光の反射・透過。マクロな視点で見ると、光の反射は、ボールが壁にあたって跳ね返るイメージと同じ。対して、量子力学の観点では、物質表面付近の電子の振動やその物質自体が光エネルギーと相互作用しやすいかどうかで反射量や透過量が決まる。このように身の回りで起きている当たり前な現象を量子力学の観点で正しく理解したいと思ったから。
Q2.「あなたが研究室を変える理由は何ですか。あなたの大学でも同専攻はあると思いますが。」
A2.「研究したい分野の実験を行う研究室はありますが、理論を突き詰める研究室はない。これまで実験の結果だけを考察し、何故そうなるのかといった理論的な部分の勉強を怠っていた。大学院へ進学する上で、一度理論から学び直し、理論と実験を紐づけた結果を出したいと思っている。そこで、専攻分野の実験・理論研究室の両方があり、〇〇といった理由も含めて大阪大学の〇〇専攻〇〇研究室へ変更しようと考えた。
今見返すと、表面的な回答でしたが、当時の学力で絞り出せる最大限のワードを発していたと思います。
人手不足の研究室がねらい目
3つ目は理系研究室の人材不足。
自身が他大学の大学院を目指すように、大学院内の人は入れ替わりが多いです。特に新規立ち上げの研究室や、いわゆる内部生のみが知るブラック研究室がある意味ねらい目。
大学院入試前にやること
進学先の大学院候補を決める
上述の内容を踏まえて、進学先を決める。この時、1つに絞るのでは無く、複数の選択肢を持つことが大事。
特に同分野の研究で選択肢を持つことで、研究室間の相対評価ができます。今何がトレンドで、入学後どういったことに取り組むことになるのかのイメージが付きやすいです。
研究室へアポを取る
進学先の候補を決めたら、志望の研究室HPにアクセスし、教授にアポを取る。
基本的にはHP内の”メンバー”のページに個人のメールアドレスが記載されています。そこから連絡先を入手するのが基本的なルートです。また、研究室によっては助教や秘書がいるので、メールするときは、CCに入れておくのが大事です。
教授は日々忙しいです。知らないアドレスからのメールに気づかずにスルーされてしまう可能性があります。こちらから確認する手段は無いので、リスクヘッジのため、宛先を増やしておくことは大切です。
研究室訪問を行う
アポが取れたら、実際に研究室へ訪問します。
教授も、自身の研究室に興味を持ってくれることは嬉しいです。積極的に質問をし、可能な範囲内で院試対策を教えて貰いましょう。
内部の学生や院生と接触できる機会があれば、過去問を貰うのも手です。とにかく恥ずかしがらずに、聞けることは聞いて、持ち帰れる情報は全て入手するべきです。
大学院院試 合格後にやること
合格後は、再度教授とアポを取り、研究室を再訪問しましょう。入学までに必要なことや、手続き関係など、積極的に聞いておくことが大切です。
また、教授は入学までに必要なこととして、”学部の卒業研究をきちんとやり切ること”と言う人が多いです。要するに、院での研究は院に入ってから頑張れば良く、今しかできない研究に注力しろということ。
【まとめ】学歴ロンダリングまでの道のり
学歴ロンダリングによる大学院進学について、院試までの流れを解説しました。
- 大学受験と比較して、大学院受験は非常に難易度が低い
- 院試前には、志望研究室を訪問し、情報を入手することに注力する
- 他大学に進学するからといって、卒業研究は手を抜かず、真剣に取り組む
後編では、実際にロンダリングした学歴で、”就職活動に有利なのか”や”ロンダリングのメリット・デメリット”を解説します。







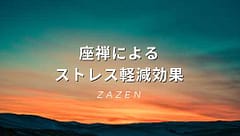
コメント